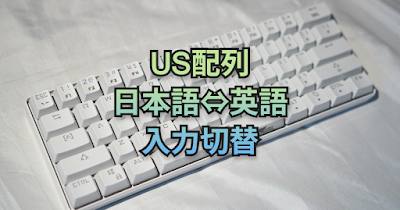Keychron K3 Max US配列 RGBホットスワップ対応【赤軸】購入レビュー
個人的に気になっていた新製品Keychron(キークロン)K3 Maxが発売されていたので、実際にAmazonで買ってみました。
ロジクール MX Mechanical miniとも悩んだのですが、海外レビューなども参考にして、打鍵感の良さや、キー配列を自分好みにできる点などからK3 Maxにしました。
K3 Maxはロープロファイルメカニカルキーボードで選んだのは「RGB・ホットスワップ対応・赤軸」で約23,000円です。(ちなみにキーボード案件は全く来ません)
Keychron K3 Maxの詳細
- キー数:87キー(日本語)・84キー(US) 【75%】
- ボディ素材:アルミニウムとABS
- キーキャップ素材(US):ダブルショットPBT(透過しない)
- キーキャップ素材(JIS):ABSにレーザー刻印(透過する)
- ポーリングレート:1000Hz(2.4GHz・有線時)90Hz(Bluetooth)
- Nキーロールオーバー:対応(無線及び有線時)
- MCU:超低電力Arm Cortex-M4 32ビット STM32F402(256KBフラッシュ)
- バックライト:RGB・White LED
- 対応システム:Windows/Android/Mac/iOS
- スイッチ:Gateronロープロファイル メカニカル
- バッテリー容量:1550mAh
- 無線作動時間:【RGB】最大40時間(RGB最小輝度時)最大78時間(バックライトOFF時)
- 接続:2.4GHz、Bluetooth、有線
- Bluetoothバージョン:5.1
- サイズ:306 x 116mm、高さ17mm(手前側)/22mm(後ろ側)
- 重量:約525g
外観
K3 Maxの特徴はキーキャップがグレーのツートンカラー+オレンジの差し色です。天板と側面はブラックのアルミ製です。
前作のM3 Proはもっとブラック寄りの色合いでしたが、M3 Maxは無印M3と同じような色合いとなりました。
裏側には滑り止めのラバーが5ヶ所ついていて、角度調整用の爪と製品情報ステッカーで、小さく技適マークも入っていました。
キーボード背面には充電用のUSB-C端子と、接続切り替えスイッチ、OS切り替えスイッチが付いています。
付属品
付属品は、2.4GHz無線用子機、交換用キーキャップ、Type-Cケーブル、Type-A to Type-Cアダプター、キーキャッププラー、スイッチプラー(ホットスワップ版のみ)です。
Type-A to Type-Cアダプターはケーブルと無線用子機を繋げるためのもので、子機をキーボード近くに置いて通信を安定させる目的です。(使わなくても普通に大丈夫)
キーキャップの交換
ESCキーをグレーに交換すると結構シックな印象に変わりますね。色合いはロジクールM750などとよく合います。
ESCキーとEnterキーもオレンジに変えた場合はポップな印象に変わります。このほかに、Mac用とWindows用のキーキャップも付属しています。
K3 Maxの使用感
打鍵感
ショートストロークで軽快な打鍵感(赤軸)
K3 Maxの赤軸はショートストロークではありますが、十分にメカニカルを体感でき、程よく高い打鍵音が鳴るのもいいですね。
最大キーストロークは約3mmで。アクチュエーションポイントは約1.7mmとなっています。ミスタイプも少なくちょうどいい設定に感じました。
通常のキー部分は素早くタイピングするとカチャカチャとコトコトの中間くらいのカチャコトくらいが鳴って心地いいです。
スペースキーやエンターキーなどはスタビライザー音が気になる製品もありますが、キークロン K3 Maxは本当に素晴らしくコトコトと静かです。
赤軸はかなり軽めの打鍵感で長時間のタイピングでも疲れにくいです。もう少ししっかりした打鍵感が欲しいなら茶軸もありだと思います。
青軸はカチカチと高い音が鳴って、茶軸よりもさらにしっかりしたフィードバックがあるのが特徴です。この辺りは好みですね。
ロープロファイルメカニカルの強み
一般的な高さのあるメカニカルキーボードも使っていましたが、打鍵感は心地いいのですがどうしてもパームレストが必要でした。
それが邪魔だったこともあり、パンタグラフ方式の薄いキーボード特にロジクール MX Keys Miniが気に入っていました。
キークロン M3 Maxは基本性能や質感がとても高いので、薄型だけど打鍵感の良いキーボードを探している方には安心しておすすめできます。
ゲームにも使える性能
ポーリングレート(1秒間でPCへと送られるデータ入力回数)は2.4GHzと有線モードで1000Hz(通常が100Hz前後)なので、ゲーミング用途でも使えます。
2.4GHz無線か有線接続ならゲームで威力を発揮しつつ、通常使用ではBluetooth接続(ポーリングレー90Hz)を使い分けることもできます。
ホットスワップ対応モデルはカスタマイズ幅が広い
ホットスワップ対応モデルなら後からでも軸を交換できるカスタマイズ性の高さも魅力です。(Gateronロープロファイルスイッチから選ぶ必要あり)
ホットスワップ非対応モデルよりも10%ほど価格は上がりますが、いろいろ試したいならRGB・ホットスワップ対応モデルはおすすめですね。
3段階の角度調整も可能
キークロン K3 Maxは直置きに加えて2段階スタンドの合計3段階での角度調整が可能です。
実際の角度はスタンドなしで「2.5°」1段階で「4.2º」2段階で「6.5º」となり、個人的には最大角度で使うのがしっくりきました。
複数OSで使えるマルチペアリング機能
キークロンはスイッチ一つでMacとWindowsの配列を切り替えることができ、有線接続、2.4GHz無線、Bluetoothでの3パターンで使えるのも強力です。
K3 Proまでは、有線かBluetoothのみでしたが「2.4GHz無線」に対応したことは個人的に大きなアップデートでした。
MacではBluetoothで問題ないのですが、Windowsの場合にはいまだにBluetooth接続があまり相性が良くない場合があります。
Windowsは2.4GHz無線か有線を使わないとBIOS画面の操作ができなかったり、スリープ解除すらできない場合もあり個人的にBluetoothでの運用は厳しかったのです。
このあたりは結構マニアックで好みの部分があるのですが、私は有線接続が嫌いでWindowsを使いたい場合には2.4GHz無線に対応は必須と考えていたりします。
全通信パターンに対応したK3 Maxは価格も上がりましたが、このジャンルでは平均的な金額設定で多機能かつデザインも良くて、幅広くおすすめできるようになりました。
RGBについて
RGBの調整(RGBモデルのみ)が若干複雑です。
- Fn+Q・Fn+A・右上のキー=ライティングモード変更
- Fn+E ・Fn+D=RGBの色合い調整
- Fn+R ・Fn+F=RGBのコントラスト調整※
※説明書には記載が無くて、キーマップと実際の動作を見ると恐らくこういう意味だと解釈しました。間違っていたらごめんなさい。
ホワイトバックライトモデルはFn+F5・F6での輝度調整と、右上のキーで点灯モードの変更が可能のはずです。
バッテリーの残量チェックはFn+B
有線接続をしていない状態で、Fn+Bを押すことで1~0キー部分でバッテリー残量を表示してくれます。
1~0まで点灯していれば満充電状態でグリーンに光り、1~9までがブルー、1~3で赤に光ってバッテリー残量が少ないことがわかります。
充電は5V1A(5W)で約2時間ほどで満充電になります。Bluetoothや2.4GHz無線接続時にPCや充電器から充電しつつ利用が可能です。
US配列の利点と注意点
正直、K3 Maxの問題点はほとんどないのですが、配列を選ぶのは注意が必要です。
個人的にはUS配列バージョンを購入することをおすすめします。JIS配列(日本語)バージョンではいくつか気になるポイントがあるためです。
US配列のみダブルショットPBT素材
なぜかK3 MaxのUS配列バージョンだけが、ダブルショットPBTキーキャップを採用していて質感が高くて指紋も付きにくいです。
PBT素材は、耐油性・耐久性に優れていますが、文字の刻印部分がバックライトで透過しないのが注意点ですね。
JIS配列は透過型のABS製
JISレイアウトの場合はABSにレーザー刻印(バックライト透過)です。ABS樹脂製も悪くはないですが、指紋が残りやすかったり打鍵感にも影響を与えます。
JIS配列の矢印キー配置は要注意
JIS配列の最大の注意点は矢印キーの配置で、US配列では素直に逆T字に並んでいるのがJIS配列では横一列に矢印キーが並びます。
これに慣れるのは結構難しいようで、VIAのキーマッピングなどで対応するのが良いかもしれません。
US配列は日本語⇔英語変換が難関(Windows)
Macの場合には外部キーボードを接続する際にJISかUSかを判別する作業が入りますが、Windowsでは設定の結構深い部分を弄らないとUS配列に変更できません。
加えて、その際にデフォルトでは「Alt + `」や「Ctrl+Space」で日本語⇔英語を切り替えるのですが、個人的には2キー使うのが面倒です。
US配列設定にするなら「PowerToys」アプリを使って「Capslock」などを変換のために使うパターンや、JISキーボードも併用するなら「ULE4JIS」というアプリを使います。
詳細は以下の記事で解説していますが、このキーボードなら次のVIA設定でも変換を行えてしまいます。

US配列で日本語入力の切り替えを簡単に行う方法【各OSごとに解説】 - plz-reference-blog
US配列キーボードで日本語入力の切り替えを素早く簡単に方法を各OSごとにまとめました。JIS配列での英数/かな変換の方法も解説しています。
VIA設定
VIAを使うことで、キーマップ変更を行うことができ、すべてのキーを入れ替えてしまえます。しかもキーボード内で記憶してくれるのも強みです。
WindowsかMacに有線接続して設定します。詳しく解説してくれている公式URL:https://superkopek.jp/pages/howtouse-via
解説は動画付きでわかりやすいので、Google Chromeを使っていればWeb上でそのまま設定ができます。
キーボードが自動認識しない場合(2024年7月時点ではまだされない)Keychron公式サイトからキーマップJSONファイルをダウンロードしてくる必要があります。
ダウンロードするファイルはホワイトバックライト版とRGB版で異なるようです。

|
| Keychron M3 Max 公式HPより |
公式ページの「キーマップをVIAで機能させる」に2つのJSONファイルがあるので選択します。(Keychron M3 Max 公式HP)
MacとWindowsを別々で設定でき、通常の状態とFnキーを押した状態それぞれ、合計4つのLAYER(0・1がMac用 2・3がWin用)をすべて自由に操作できます。
私はBackspaceやEnter周りを結構弄りました。誤入力が頻発したのでpageup・pagedown/home・endなどをすべてEnterかBackspaceに変えてしまいました。
VIAのアプリ自体も使いやすくて、変更したいキーを選択して変えたいキーを選ぶだけです。Fnキーを含むすべてのキーを変更可能なので自由度は非常に高いです。
英語⇔日本語(英数/かな)切り替えについて
前提としてキーボードをUS配列として認識させます。
設定「時刻と言語」→「言語と地域」の「日本語」→「言語のオプション」→キーボードの「レイアウトを変更する」にて「英語キーボード(101/102キー)」を選択。
「Special」の一番最後にある「Any」を選択するとキーマップを手動で入力できます。
■任意のキーに A(KC_GRV) と入力すると全角/半角キーと同じ動作になります。私は「Capslock」キーを変更しました。
また、左右「Alt」キーを使って「英数/かな」の変換も行えます。(長押しでAlt動作)下記の太字部分を「special」の「Any」にて記載します。
■左の「Alt」キーに MT(MOD_RALT,KC_HANJ)
⇒単押しだと「英数」キー、長押しで「左Alt」キーとして動作
■右の「Alt」キーに MT(MOD_RALT,KC_HAEN)
⇒単押しで「かな」キー、長押しで「右Alt」キーとして動作
設定したものはキーボードに記録されるため、そのままほかの環境でも使えます。
ロジクール MX Keys Miniとの比較
比較対象としてはMX Mechanicalなどが一番近い性能だったりしますが、手持ちに無いためコンパクトキーボードのMX Keys Miniと比べました。
パンタグラフとメカニカルの違い
MX Keys MiniとK3 Maxは薄型ワイヤレスキーボードとしては近いのですが、パンタグラフとメカニカルという方式の違いが一番大きいです。
パンタグラフ方式というのは、ノートPCなどによく使われるラバー+プラスチックの支えを用いて薄いけれど比較的打ちやすいです。
ただ、キーストロークが浅い(MX Keys Miniは1.8mm)ゆえに底打ち感が強かったり、浅いラバーを使う故に長時間の打鍵では疲れが出やすい場合もあります。
メカニカル方式はスイッチ+スプリングを用いており、キーストロークは深めで打鍵音もちょっと大きめだったりします。
K3 Maxのロープロファイルメカニカルでは、約3mmのキーストロークで浅くはあるのですが、パンタグラフより指への負担が少ないように感じます。(軸の選択などにもよる)
打鍵感は好み
打鍵感については好みの問題なのですが、パンタグラフ方式ではMX Keys Miniも非常に扱いやすいキーボードです。
MX Keys Miniは、キーストロークが浅くても程よいフィードバックと全体的な質感の高さ、さらにキートップの窪みがミスタイプを減らしてくれる気がします。
キークロン K3 Maxは言葉では伝えにくいのですが、MX Keys Miniとは違う方向での良さがあります。
K3 Maxは、ロープロファイルメカニカルキーボードとして打鍵感が良く、全体的な完成度がとても高いです。
特に赤軸は押下圧が軽いために、MX Keys Miniよりも軽快に打鍵することができます。
ストローク量自体も比較すると1mm以上多くて、指の動きもそれなりに大きくなるのが好みが分かれる部分でしょう。
キーボード高さなど
手前側の高さはやはりパンタグラフ方式のMX Keys Miniが低いですね。個人的にはK3 Maxの高さで十分問題なく平置き(パームレストなし)で使えます。
ロープロファイルの利点はパームレストなど無しでシンプルなデスクにできることだと感じています。
※この高さでもパームレストが欲しいと感じる可能性はあります。K3 Maxはパンタグラフの薄いキーボード+1cmくらいの高さです。
薄型キーボードとしてどちらもおすすめ
総じてどちらもレベルが高いです。浅めでノートPCのような打ち心地が好みならMX Keys Mini、薄型でもメカニカルの軽快な打鍵感を求めるならK3 Maxがおすすめです。
MX Keys Miniを細かくレビューした記事もあります。この時はゲーミングキーボードのG913 TKLとも比較しています。
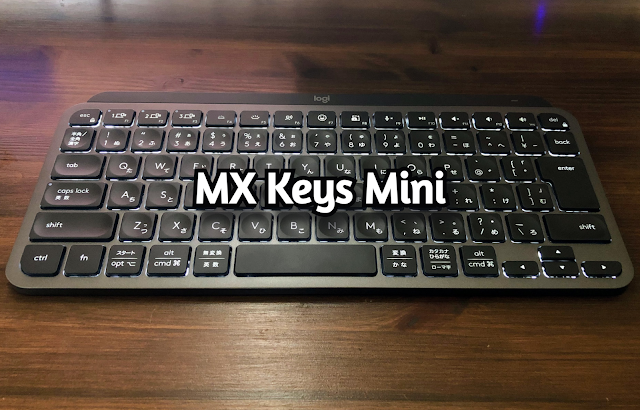
ロジクール MX Keys MiniのレビューとG913 TKLとの比較【仕事用最強キーボード】 - plz-reference-blog
MX Keys Miniを購入してレビューしました。同じくロジクールのハイエンドゲーミングキーボードG913 TKLとの比較も行って、事務作業最強と言われるのはなぜかを考えました。
まとめ
キークロン K3 Maxを実際に購入レビューしてみました。ロープロファイルメカニカルキーボードとしての完成度は非常に高い製品です。
普通に約20,000円前後するキーボードは高いですが、タイピングを一日される方は打ちやすくて疲れづらく、ゲーム用にも使える高いスペックがあります。
薄型ワイヤレスのロジクール MX Keys Miniとも比較してみましたが、打っていて楽しいのはK3 Maxでしたね。(個人的感想)
K3 Maxをキークロン公式のホームページから購入すると価格が安いのですが、技適が通っていない場合もあります。
しっかり日本で使うには正規代理店である「kopek」から買うのが正解です。ただ、Amazonで買っても結局「kopek」からの発送となっていました。
kopekでもAmazonや楽天市場などでも値段は同じで、ポイントも付く点などを考えたらAmazon等で買うのがお得でしょう。
K3 Maxには、JIS配列バージョンやホワイトバックライト(軸固定)バージョン等もあります。
AmazonのKeychron K3 Maxのバリエーションは次のリンクからチェックできます。
■Keychron K3 Max 製品一覧
XVXロープロファイルキーキャップ
その後、XVXロープロファイルキーキャップ(ブラック・US配列専用)に付け替えてみました。PBT素材で文字が透過するタイプです。
実際の打鍵感には多きな変化はなく、XVXに変えて全体的にキートップが平坦になったために個人的には指の動きがスムーズにできるようになったと思います。
打鍵音も私の感覚ではほとんど変化していないです。(※スタビライザーがあるキーは少し加工しないと異音が鳴る場合あり)
表面は純正品の方がきめ細かい処理がされており、XVXは比較するとちょっとザラザラしています。(これは比較してでの話なので、実際はどちらもサラサラで気持ちのいい仕上がりです)
Keychron K3 Maxに合うブラックのキーキャップとしてしっかり使える製品でした。多少の加工が必要でしたが、詳細はnote記事に書いています。

XVX ロープロファイルキーキャップ レビュー【Keychron K3 Maxのイメージチェンジ】|参考サイトの管理人
Keychron K3 Maxに合うブラックのキーキャップを探し、Amazonで見つけられたのがXVXキーキャップでした。 XVX ロープロファイルキーキャップの特徴 セットはほぼすべてのキーが含まれている XVXキーキャップは118キーのセットになっていて、60%~100%キーボードまで対応しています。AltキーやEnterキーはサイズ違いも入っています。(US配列のみに対応) セットの中にはWindows用とMac用の2種類が入っているのでどちらにも対応できるのが親切ですね。 PBT素材と文字の透過 PBT素材はABS製と比べて耐久性が高くて指紋は付きにくいです。ABS
Keychron K3 Max US配列 RGBホットスワップバージョンの楽天市場やYahoo!ショッピングのリンクは以下から見れます。